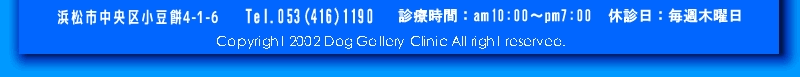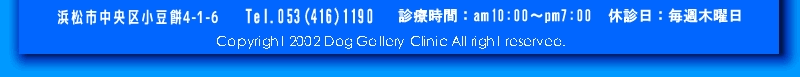犬の健康管理 vol.8
犬のリンパ腫
リンパ腫は、悪性リンパ腫またはリンパ肉腫とも呼ばれる悪性の腫瘍です。
リンパ球が骨髄以外の色々な部分で腫瘍性に増殖する疾患です。
犬の腫瘍の中でも発生率が高く、比較的良く遭遇する腫瘍のひとつです。
発生年齢は6ヶ月齢~15歳齢と幅広い範囲で認められます。発生リスクの高い犬種はG.リトリバー、シェルティ、シーズー、ボクサー、スコティッシュなどがあげられています。逆にリスクの低い犬種としてダックスフント、ポメラニアンが挙げられています。
リンパ腫は発生する場所の違いによりいくつかの型に分類されています。
犬のリンパ腫の病型
| 多中心型 |
犬のリンパ腫では最も多い型です。体表リンパ節が腫大しています。見つけやすいのは下顎リンパ節ですが、浅頚、腋下、鼠径、膝下などのリンパ節も腫大し、疾病の進行に伴って肝臓・脾臓・骨髄にも広がって行きます。初期には1個のリンパ節のみが腫大し、進行に従って体重減少・食欲不振・元気消失・発熱等の症状が現れます。リンパ節が腫大する疾患はリンパ腫の他にも全身性感染症(炎症・真菌・細菌・ウイルス等)や過形成等がありますから、これらとの鑑別が必要になります。 |
| 縦隔型 |
リンパ腫の約5%に認められ、胸腔内にある前縦隔リンパ節または胸腺の腫大を特徴とします。胸水が貯留し肺が圧迫されることにより呼吸困難が生じることがあります。また、高カルシウム血症が良く認められます。 |
| 消化器型 |
リンパ腫の5~7%に認められるタイプでメスよりオスに多いと報告されています。腸管にリンパ腫が広がっていると吸収不良・体重減少・食欲不振・低タンパク血症等が生じます。 |
| 皮膚型 |
皮膚に発生する型で、孤立性のこともあれば全身に多発することもあります。このタイプには口腔粘膜に発生するものもあります。 |
| 節外型(その他) |
眼、中枢神経系、骨、鼻腔等から発生するものを含みますが、非常にまれなタイプです。 |
さらに、どんな型のリンパ腫であっても現在ペットのリンパ腫がどの程度の進行度であるかを調べることは治療とその予後に関して非常に重要です。そこで、リンパ腫の進行度を表すステージ分類について説明します。
犬のリンパ腫のステージ分類
| ステージ Ⅰ |
1個のリンパ節または単一のリンパ系組織に限られる場合 |
| ステージ Ⅱ |
複数のリンパ節の限局性病変の場合。 |
| ステージ Ⅲ |
全身のリンパ節に波及している場合。 |
| ステージ Ⅳ |
肝臓、脾臓に浸潤している場合。 |
| ステージ Ⅴ |
血液、骨髄、その他の臓器に発現した場合。 |
ステージはさらに臨床的サブステージa(臨床症状なし)またはb(臨床症状あり)に分けられる。臨床症状とは元気消失、食欲不振、嘔吐、下痢などの様々な症状のこと。
|
犬のリンパ腫の予後因子
| 全身状態 |
治療開始前に元気消失・食欲不振・嘔吐・下痢・貧血・肺炎などの全身症状を示している患者は経過が悪い。
|
| 臨床ステージ |
ステージⅠ~ⅢはステージⅣ、Ⅴよりも治療反応が良い。 |
| 高カルシウム血症 |
高カルシウム血症を併発している場合には経過が悪い |
| 治療反応 |
最初の治療により、速やかにリンパ腫の消失した患者は予後が良い。 |
| 病型 |
多中心型は縦隔型よりも予後は良い。 |
| 性別 |
メスはオスよりも予後は良い。 |
| 体重 |
小型犬は大型犬よりも予後が良い。 |
| ステロイド投与歴 |
ステロイド剤の単独長期間投与は、がん細胞の化学療法剤(抗がん剤)に対する耐性を生じやすくさせるため、その後の治療反応率が低下する。 |
犬のリンパ腫の診断方法
| 触診 |
全身を触診し、リンパ節の大きさ・固さ・形・周囲組織との関連性、各種内臓の大きさや、腹腔内のしこりの有無を調べます。 |
| 血液検査 |
血液中の異常リンパ球の有無を調べ、治療に先立つ全身状態の把握のために実施します。 |
| レントゲン検査 |
胸腔内のリンパ節の腫れを探します。また、腹腔臓器の状態(大きさ・位置)やリンパ節の大きさを調べます。 |
| 超音波検査 |
腹腔内臓器・リンパ節の状態を検査することができます。レントゲンでは分からない、臓器や腫瘤の内部構造・血管構造等が分かります。 |
| 細胞診 |
腫大したリンパ節や異常な臓器には、それぞれの臓器に応じた方法でバイオプシーを行います。通常は針生検を実施し、異常リンパ球の増殖を確認することで速やかに診断が可能です。 |
| 病理検査 |
細胞診で診断が付かない場合には麻酔下による切除生検にて1箇所のリンパ節を全て切除して検査をしたり、トゥルーカット(瞬間的に小さな組織を採取する器具)や開腹手術により臓器やリンパ節を切除して病理組織検査に提出し、診断を確定する必要があります。 |
クローン性解析
NEW!!
|
病理検査に替わるもう一つの方法で、PCR法をもちいて、リンパ系腫瘍であるか否かを判定します。さらにそれがB細胞型であるかT細胞型であるかが判るので、リンパ腫の予後予測や治療方針の策定に有用です。ごく少量の細胞での検査が可能であり、感度の高い方法です。 |
治療方法
リンパ腫の治療に用いられる治療法で主なものを挙げます。現段階では、犬のリンパ腫の治療は根治(完治)ではなく症状の緩和を目的とします。人の医療のように骨髄移植や激烈な化学療法を行うことはなく、リンパ腫による全身症状を改善して、リンパ腫とつきあいながら、よりよい生活をしてゆくことが目標となっています。
| 化学療法 |
リンパ腫の主な治療法は全身に効く治療法である化学療法(いわゆる抗がん剤)です。使用する抗がん剤はその子の状態によって違います。癌細胞は抗がん剤に対してすぐに耐性を獲得するため、数種類の薬品を組み合わせて使用することが必要です。
幸いなことにリンパ腫は化学療法に非常に良く反応するため、治療前には状態の悪かったペットが、抗がん剤の投与後には見違えるように元気になり、あたかも完治したかのように思うことがよくあります(「寛解」:臨床徴候が消失した状態。いわゆる完治とは異なる)。しかし、癌細胞が見えなくなった状態であってもまだまだ非常に多くの細胞が生き残っており、すぐに元の状態まで戻ってしまいます。そこで、状態が改善した後も治療を続ける必要があります。
適切な治療を行ない、ペットが病気とは思えないくらい元気な状態で生活していても、リンパ腫の場合には「再燃(再び癌細胞が増殖を開始し、臨床徴候が発現してくること)」は避けられない問題です。その場合には、それまでとは異なる種類の薬剤を使用して、再度の寛解を目指し、新しいプロトコールで治療を行います。この、治療→寛解→維持→再燃→再寛解、という流れは、リンパ腫に特徴的なものです。
リンパ腫では通常、数ヶ月~1年以上という単位で継続した化学療法を行います。治療の間にはリンパ腫による症状や抗がん剤の副作用などの様々な問題が生じる場合があります。それらを乗り越えて治療を継続して行く努力が求められてきます。
ひとつのデータによれば、リンパ腫と診断されたイヌが、無治療に置かれた場合の中央生存期間は6週間と言われています。最近では様々な薬剤の組み合わせにより1年を越える生存を認めるペットも少なくはありません。
|
| 外科療法 |
リンパ腫は全身性疾患であるため、通常は外科療法の適応ではありません。しかし、皮膚に孤立して腫瘤を形成していたり、眼球や腹腔内でも孤立して病変をつくっている場合には、手術により大きなリンパ腫の塊を取り除き、癌細胞の数を減らしてやることは治療上有効です。(腫瘍細胞の数を減らしてやると、腫瘍細胞は元に戻ろうとして活発に増殖を始めるが、化学療法や放射線療法は、そのように活発に増殖する細胞に対してより効果を発揮する。) ただし化学療法との組み合わせが必要です。 |
| 放射線療法 |
リンパ腫は放射線への感受性が非常に高い為、治療効果の高い方法です。しかし、リンパ腫は全身性疾患であるため、局所療法である放射線治療だけでなく、全身療法である化学療法と組み合わせることが必要になってきます。 |
|